|
聞き手:長年アフリカ研究をされてきている遠藤先生ですが、アフリカを研究対象にされたきっかけをお聞かせください。
遠藤氏:「何故アフリカを研究しているのか」とよく聞かれるが、その質問に答えられたらアフリカ研究から卒業してもいいかと思うぐらい、自分自身でも明快な答えは分からない。関心を持ち始めたのは高校から大学にあがる頃で、内戦で飢餓に苦しむエチオピアについて、BBCかどこかの海外メディアの映像をNHKのニュースかドキュメンタリーで見たのがきっかけだった。もちろん、その頃は「アフリカ」という地域的な視点ではなく、飢餓や食糧難といった問題が自分と同じ世界に存在するという現実を漠然と理解する程度だった。
大学に入って、地球環境問題や食糧問題など、いわゆる経済モデルや国際法の枠組みでは捉えきれない問題が特に噴出している地域としてアフリカに興味を持つようになった。また、当時はアフリカに興味を持つ学生もまだ少なかったので、他の人と違うものを選びたいという意識が働いたところもある。
しかし、当時はアフリカをテーマにした講義は少なく、本腰を入れて勉強した最初の一歩が、SADC(Southern African
Development Community:南部アフリカ開発共同体、当時のSADCC)と南アフリカ共和国(南ア)の関係について書いた卒論だった。当時のSADCC(Southern
Africa Development Coordination
Conference:南部アフリカ開発調整会議)は、アパルトヘイト(人種隔離政策)を進めていた南アの経済的支配からの脱却を目指して、周辺国の南部アフリカ諸国が組織していた。80年代はこうした国々とアパルトヘイト末期を迎えていた南アとの関係が微妙な時期で、当時、少ないアフリカ情報の中でもこの地域については比較的多く情報を入手できたので、卒論テーマに選ぶことができた。
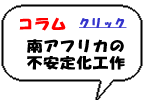 加えて、イギリス出身の活動家で学者でもあるジョセフ・ハンロンがちょうど当時南アの「不安定化工作」について分析しており、彼が執筆した本、Beggar
Your Neighbours: Apartheid Power in Southern Africa とApartheid’s Second
Front(『隠された戦争 : アパルトヘイトと黒人諸国』 北村文夫訳、新評論)に刺激を受けたところもある。 加えて、イギリス出身の活動家で学者でもあるジョセフ・ハンロンがちょうど当時南アの「不安定化工作」について分析しており、彼が執筆した本、Beggar
Your Neighbours: Apartheid Power in Southern Africa とApartheid’s Second
Front(『隠された戦争 : アパルトヘイトと黒人諸国』 北村文夫訳、新評論)に刺激を受けたところもある。
聞き手:紛争・国家について専門性を深められたのは大学院の時ですか?
遠藤氏:国際関係論の専門的な知識は大学院で学んだが、指導教官が比較的柔軟な指導方法をとっていたこともあり、修士論文では国際関係よりも南アの国内政治に焦点をあて、南アの政治変動がどういうプロセスを経て成り立っているのかを分析した。その過程で、不安定化工作など国外に向けた政策であっても、その政策形成には国内的要素が深く関与していることに気づいた。ある国の政治形態を方向付ける要素は、外生的要因だけでも内生的要因だけでもなく、国家間同士の緊張感によってもたらされていることを初めて実感することになった。
その後、当時、在籍していた東京大学ではアフリカを専門とする指導教官がいなかったので、博士課程は英国の大学院に留学した。
英国ではフィールド調査が必須とみなされており、アフリカへ渡る機会を得た。修士までは南アについて研究していたが、博士論文では、あえて調査対象国の軸足を周辺国のザンビアとボツワナに移した。南アは1990年にネルソン・マンデラが釈放され、アパルトヘイト終了が目に見えていた頃だったが、現地の情勢が不透明だったのと、南アの情報は日本でも入手できたので、あえて選択肢から外した。
日本では情報が得にくいザンビアとボツワナを対象国に絞り、当時の比較的新しい概念だった「市民社会」(Civil
Society)と民主化の関係を研究しようとした。しかし、現地では「市民社会」の概念やNGOという言葉がまだ浸透しておらず、市民社会と言える様な実態が具体的にどのような形で存在するかどうかを確認することから始めなければならなかった。
現地ではキリスト教系のグループ、女性保護の観点から活動している組織、労働組合、農業共同組合、赤十字などが活動していたが、NGO一覧のようなものもなく横のつながりがないため、見つけ出すのには苦労した。そこで、民主化直後に登場してきた団体にも焦点をあてることにした。
しかし、今度は何を調査して分析すればおもしろい論文になるのか、そのテーマを絞るのに一苦労だった。ザンビアとボツワナの比較研究を予定していたこともあり、両国に共通したものを探さねばならなかった。結局、人口政策の領域で活動しているグループを候補とするめどをたて、ザンビアで3ヶ月ほど情報収集をしたのち陸路でボツワナ移動した。
国境を越えただけでこうも違うのかと感じたのは、ビールを見た時だった。ザンビアでは瓶ビールしかなかったが、ボツワナでは缶ビールが普及しており、ボツワナのある種の経済的な先進性とでもいえるようなものを感じた。
他方、ボツワナには民族の違いによる差別があった。ボツワナ政府は野生動物保護区内に居住する小数派のバサルワ(ブッシュマン)の移住を推進していたが、そうした誘導政策で都市に移転してきた少数派民族を多数派(ツワナ)が受け入れていなかった。また、移民労働者として居住してきた中国人に対しても蔑視している節がすでにその頃からあった。
聞き手:市民社会の視点から政治変動を観察されて、おもしろい発見はありましたか?
遠藤氏:興味深かったのは、ボツワナが民主化の成功例としてよくあげられるが、実はザンビアの方が開かれた民主主義と思える部分があったところだった。
まず、「市民社会」を観察するためには、その対となっている国家も見なければならない。政策領域の意思決定の中にどれだけ「市民社会」など各種団体の声が反映されているか、また、「市民社会」の役割がどう位置づけられているかは、国家との関係性の中で分析される事象なので、国家(より操作的には政府)との関係を無視して「市民社会」を分析することはできない。例えば、現在の関心に少しひきつけて言えば、今のソマリアは政府が事実上崩壊しているので、政府のないソマリアに「市民」はいるのか、「市民社会」はあるのか、という議論が必要となりうる。
ボツワナは選挙制度を敷き多党制を導入し、経済成長も上向きで、アフリカ地域の中では珍しく民主化に成功したと言われる国である。しかし、市民参加というミクロな政治プロセスを見ると、国家が社会政策のあらゆる側面をコントロールしてしまうため、NGOや市民グループが政策形成の領域に参加する余地がない。彼らが政府機能を代替して活躍する場もなければ、もともとあったNGO等の活動自体を政府が抱きこんでしまうため育成されないといったことが特徴となる。
選挙などの手続き上にみる政治体制の民主化と、政策領域への市民参加という実態からみる民主化は必ずしもシンクロしないということが観察と分析の結果わかってきた。
聞き手:著書の中で、家産制国家(パトリモニアルステート)など利権配分機能として国家が存在している場合、資源力の分配権利を国家が握っている間はその政府は強さを持続させるが、冷戦の終結などによって外部からの援助が減少した国などで、政府が分配できる資源が減ると求心力が弱まり、紛争など社会的不安定要素が生じてくる、と書かれておりますが、ボツワナ政府の強さは、資源の利権配分を集中して持っていることに因るのでしょうか?
遠藤氏:ボツワナは特殊なケースといって良いだろう。確かに、政府機能が弱い国家が多いアフリカ諸国の中で、ボツワナ政府は資源の利権配分をきっちり握って管理している。ボツワナが持つダイヤモンド資源の規模は他国とは比べ物にならないほど大きく、砂漠の奥底にあるため一般人が掘りにいけるものでも(他の紛争ダイヤの産地でのように)労働集約的に採れる鉱物でもない。デビアスなどの巨大資本でないと成り立たない資本集約型の鉱業で、政府はこの一大国家プロジェクトの利権配分を独占的に管理し、早い段階から経営的思考をもって事業を成り立たせてきた。こうして財源が確保できているためか、ボツワナ政府は資源・資金の分配機能だけでなく、行政サービスの提供機能もきちんと果たしている。
加えて、ボツワナでは汚職も少なく、他のアフリカ諸国にはない特徴としてモラルの浸透性の高さがある。指導者の第1世代である初代大統領のカーマ大統領、2代目のマシーレ大統領らの「良き遺産」とも言われる。ボツワナ国家の特異な成り立ちによるものと思うが、詳しい分析をするとなれば脱植民地主義時代に至るまでの歴史をさかのぼる必要があるし、実際そうした研究が存在する。現代史を見ても、他のアフリカ諸国にあるような、冷戦期にアメリカや旧ソ連の援助に依存してきた利権分配型国家(クライエントステート)的要素はない。
聞き手:国家に発展段階というものがあるとすれば、家産制国家は民主国家へ移行する前段階と説明する議論をよく耳にしますが、それは当てはまると思われますか?
遠藤氏:ヨーロッパの歴史ではそういう経緯をとったかもしれないが、今のアフリカを見ると必ずしもそうとは考えにくい。これまで家産制国家的であったものを解消させるテコになりうるのが何であるか分からないし、ヨーロッパと違ってアフリカの多くの国は体制を民主化したことが家産制の終焉には繋がっていない。しかも、現在見られる家産制の特徴は、昔の絶対君主による支配とは違い、制度化されず表面にでてこない社会生活の側面を動かしているので、ヨーロッパ近代をめぐる議論とは次元が違う。
聞き手:アフリカで「民主化」という時、その言葉が具体的に何を意味するのかよく分からないのですが・・・。
遠藤氏:私もアフリカの「民主化」が具体的に何を指すのかは一義的にはよく分からない。欧米諸国や世界銀行が援助資金を出す際に、援助供与の条件、つまり「コンディショナリティ」として被支援国に突きつけた「民主化」は、複数政党への移行と公正な選挙実施だった。ところが、制度を民主化しても欧米諸国のような民主主義概念は生まれてこない。そこで、新たな支援対象領域として国の政治機構や基本的な制度のあり方(ガバナンス)を挙げ、足りなかったと思われる改革を促しているのが今のアフリカ支援。
しかし、民主主義が根付かない根本的な原因は民主化を急かしてしまったところにある。その一例が憲法改正。例えば、自国のイニシアティブで民主化を進めた南アは大々的な憲法改正ができたが、かなり長い時間をかけて議論していた。ところが私が観察していたザンビアでは、コンディショナリティに沿って複数政党制を敷き、公正な選挙の実施という制度面の変更を憲法に盛り込んだだけで、憲法に位置づけられている大統領権限は改革されずじまい。結果として、憲法は大統領個人の意思による修正の余地を残すなど、独裁的支配の要素が継続されてしまった。
アフリカは民主化を自己流に「消化」した(あるいは「飼いならした」)
。彼らの従来の思考・概念を変えずに、制度だけを民主化し、民主化の精神は受け流してしまったところがある。「Constitution without
constitutionalism」とよく言われるが、文言上の憲法改正をしたところで憲法を順守するといった意識変革はされなかった。これは外部からの投入であるコンディショナリティの限界とも難しさとも指摘できよう。
聞き手:援助機関側が思い描いていた「民主化」が達成されなかった一方で、コンディショナリティがもたらした良い意味での社会変化もあったと思われますか?
遠藤氏:コンディショナリティは、表現の自由の確保や人権保護の状況改善など、社会環境の開放化を促したと思う。表現の自由が確保されたことで情報媒体機能(メディア)が多様化し、国民が得る情報量が増えた。また、複数政党制への移行により一党体制ではなかった議論がされるなど、国民に選択肢を与え、有識層の育成にも貢献している。
評価は比べる基準を何に設定するかによって変わってくる。従来と比較すれば着実に変化が生じていても、強い期待のもとで行われた改革だと目的が達成されなければ否定的な評価になってしまう。
アフリカの場合、全体的には何かしらの変化はあるのだが、政治のある側面だけを見ると旧態依然であると評価されるケースが多い。更に、そうした微妙な時期に石油が出てきたり外国から資金が入ってきたりと、国を取り巻く状況も変化するので、評価はより複雑になってくる。
聞き手:過去の民主化に対するコンディショナリティが必ずしも効果的でなかったことを考慮すると、民主化に対するコンディショナリティは今後、もっと厳格であるべきなのでしょうか
?
遠藤氏:強弱の問題というよりも、コンディショナリティによってもたらされる結果を、想像力を持って予測することが必要だと思う。理想的な将来像を描いてコンディショナリティを課すことも大事だが、過去のケースを見ると、コンディショナリティによって導かれた政策変更が社会に及ぼす影響の多様性について、あまり考えていなかったのではと思える節がある。
行政、司法、立法の三権分立が成り立っていない国もあるので、民主化や国政機能の強化を目指したコンディショナリティをつけるのであれば、憲法改正など、民主主義の基礎にあたる部分をきちんと構築できる改革を促す仕組みがあっていいと思う。ただ、あまりに細かい指定をつけすぎると内政干渉になるので、そのバランスが難しい。
聞き手:アフリカの国家についての議論で、アフリカの「国家」は大衆を捕捉できていないということが良く言われますが・・・。
遠藤氏:国家は国内的領域と国際的領域の問題が交差するところにある独立体(エンティティ)を指すが、その概念は多様で、国家と政府を同意義語として扱うこともあれば区別することもある。また、国民を含めた独立体を国家とすることもあれば、行政機能を持つ機関だけを指すこともある。様々な理解の仕方がある中で、国家が社会のどこまでを捉えているかという議論がつい最近まで行われていた。ゴラン・ハイデンは社会への「浸透力」という概念を持ち出し、国家の政策や市場経済原理に左右されず自律性を持った農民を「捕捉されない小農」と表現したが、この理論に対する批判もある。
そもそも、アフリカ諸国を独立させた段階では、国際法上の単位として「国家」を見ていたので、国内社会への浸透性について考えていなかったし、要求もしていなかった。コンゴ(民主共和国)は首都キンシャサ近辺に行政機能があるというだけで国家として成立したほど、領土内にいる国民との関係性については無関心だった。
現代のアフリカ諸国を見た時に、両極端に位置づけられるのがボツワナとソマリア。ボツワナは行政機能がしっかり管理された国家で、開発国家とも行政国家とも言われる。他方、ソマリアは国際法上国家としての地位を維持しているが、「無政府(Stateless)」と言われるように、内戦により行政機能を果たすべき政府機能は失われている。幻影国家(Phantom
State)とも呼ばれるが、ソマリアに住んでいる人達は国家という枠組みがなくても商業活動が営め、経済も活性化しているので、国家を求める内発的な動きがない。日本を含む20世紀型の福祉国家では、国家の行政サービス提供機能への大衆からの期待が高まるものだが、アフリカではそういうことがおこりにくい。
ソマリアの無政府状態は何者にも干渉しないという意味では、究極のリベラリズムともいえる状況だが、コントロール不能な地域はテロの温床になりかねない危険性を有しうる。国際社会がソマリアに何かしらの政府機能の設立を望んでも、同じ領土における統治をどのような政体のもとでおこなうかについて今後も大きな対立が予想され、当面その青写真を描くことが困難な情勢であると言わざるを得ない。その間、ソマリア国家が国際的に認識されている限りにおいては現状のまま存続することになる。
こうした諸事情を踏まえると、アフリカにおける「国家」は何が問題なのかと問われても一言では答えられない。「政治とは食べることであり、食べられるために国家がある」という言い方がある。このレトリックはケニアやザンビアでよく用いられるが、意味するところは、国家は行政機能を果たすためにあるのではなく、あたかも一つのケーキのようにその国の利権配分をより多く獲得する場、資源の一つとして見られている。
聞き手:近年、援助も国家を単位としたものに集中していますが、このように政府が家産制的性格を持ち、かつ大衆との関係がゆるいところでは、政府に援助が集中してしまうのは危険とも思えるのですが、その点はどうお考えになりますか?
遠藤氏:そのとおりで、援助のやり方はよく考えなければならない。日本は援助を外交ツールとして位置づけている。外交というのは政府間同士のやりとりで、日本の外交目的は国際的な名誉ある地位を占めることや国連機関で日本の影響力を確保することかもしれない。しかし、日本政府を代表して他国と交渉する立場にいる一部の邦人外交関係者に裨益をもたらす援助に、どれだけの意味があるのか考える必要があると私は思う。
日本の援助は日本の国益を満足させるために用いればよいと割り切り、アフリカ諸国は家産制の性格を持っていると認識した上での援助行為、資金供与であれば、それはそれでいいのかもしれない。しかし、援助の目標が日本の国益を追求した外交目的に限らないのであれば、別のアプローチもありえるだろう。
聞き手:そこで人間の安全保障という概念が関与してくると思いますが・・・?
遠藤氏:日本が「援助は外交ツールの一つ」と表向きは位置づけつつも、別の形で援助する方法を模索するとすれば、人間の安全保障というアプローチが新領域になりえると思う。ダウンサイド・リスク(個人の生活状況が悪化する危険性)に焦点をあてた援助を看板に掲げることによって、公平な分配機能を果たさない政府を迂回した援助ルートの確保が可能になる。表面上は政府との関係を保ちつつも、迂回ルートをつくるなど賢くやらないと、本来、助けたいと思っている人達に援助を届けられない。
しかし、外交の観点から言えば、日本政府が欲しいのは被支援国政府の声。民衆に感謝される援助を実施したとしても、その国が国連改革で日本の意見に賛成してくれるとは限らない。国民の意思と連動して動く政権であればいいが、アフリカの国家の現状ではそうした期待をするのは難しい。
こうしたことを踏まえると、迂回ルートを作るリスクと援助の結果が政治的目的に結びつかないジレンマに日本が向き合えるのかという課題が見えてくる。しかし、現状は理念と現実が離れすぎているのではないかと感じる。外交ツールと言いながらも、実質はすべてがそれほど繋がりあるようには見受けられないからだ。
聞き手:非政府による援助の一つとして、NGOを通じたサービス・デリバリーも最近は注目を集めていると思いますが。
遠藤氏:NGOと連携したフレームワークを目指すことは誤りではないが、先方の活動内容、実行力、許容範囲を見抜く能力が足りないと実効性は上がらないだろう。ひとつには、「NGO」の定義が曖昧なため、実態機能に統一性を持たせられないという問題がある。そのため、NGOが実際にどのような活動をして機能を果たしているかの精査が不十分な結果、渡した資金の使途が不明になってしまうということがままある。
他方、評判の高いNGOは方々から資金が集まってくるもので、資金供給が過剰になりすぎると、かえって実行機能を低下させてしまい、結果としてそのNGOをつぶしてしまうということがある。NGO支援に活発なノルウェーやスウェーデンでも精査能力が十分にあるとは言えない。ドナー側にも予算執行という責務があるのは分かるが、NGOへの資金提供は慎重にやる必要があるし、そのためには現地にNGOの実行能力を分析する専門家を貼りつけるなど、現地レベルの機能強化が求められる。
聞き手:研究者として、実務にはどういう距離感をもって関わっていらっしゃいますか?
遠藤氏:私自身は純粋な学問的関心から研究世界に入っていることもあり、政策提言するよりも、ある一般的な政策がどういう意味をもたらすかということを分析していきたい。
外部者がある国の政策形成に関わるのは非常に慎重でなければならない。例えば、紛争地域でDDR(Disarmament,
Demobilization,
Reintegration/武装解除、動員解除、社会再統合)プログラムを推進させる動きがある。最初の「D」である武装解除は、外部の人から見れば紛争解決のために望ましいステップと思うだろう。しかし、武器のある生活を送ってきた人達にとって、武器は自己実現や現在の地位を獲得するために必要な道具で、彼らの生き方そのものを象徴しているかもしれない。武器を手放すことは自己否定につながりかねない、という議論も最近ではなされている。
外部から見ると望ましいと思われる変化は、その社会に本源的変化をもたらす可能性がある。まずは現地の状況を理解し、どう関わるか判断しなければならない。しかし、外部からの投入だけでは社会の向上は生まれず、社会変革を実際にリードできるのは内部者だけである。それゆえ、現地の意味世界をよく理解することが大切だろう。武装解除を促す前に、武器を持つ意味をより深く考える必要がある。そのためにも、私自身は、政策を通じて拙速に何かを促すよりも、政策としてできた枠組みが社会にもたらす意味を考えたいし、また、そうした思考を持つ人材を育成していきたい。
| 
